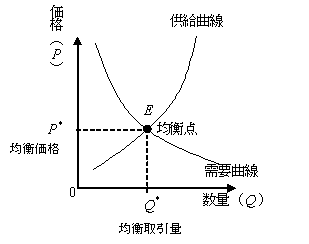こちらの記事から派生した議論を再燃させないためにまとめておきます。まあ人間、すぐに同じ議論再燃しますが。。。
スタートはここ。
ありがとうございます。飯田先生の本なども読んでますので、MMTへの賛否は別として概ね理解の通りでした。やはり池田万作氏のロジックまでいくと、明確に誤りと考えて良さそうですね。 https://t.co/OMriLS8I0h
— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) January 11, 2020
数式モデルに関してはMTPLページもご覧ください。
そうですね。ただ、私の提案するモデルのように定式化した議論をもちこむと、「税をコントロールすればインフレはたしかにおさえられる」という定量的な規範的議論を考慮する必要が出てきます。(これへの建設的批判方法は、「税を裁量的にコントロールできるのか」などです。https://t.co/JuCL3SyaMR
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 11, 2020
ありがとうございます。一読して私が感じたのは「財政出動→増税→財政出動」を繰り返せば政府は極大化をしていき、社会民主主義国家になるのではないか?という点でした。そしてご記載の通り、増税は(財政出動も)様々な利権が絡むので、論理的にオン・オフするのが非現実的であるのも難点かなと。
— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) January 11, 2020
私の提案するモデルによればデフレ対策(インフレ化)のためには財政出動よりも減税のほうが効果的ですので、「政治家は定量的な議論をできるひとばかりである」という仮定のもと(現実は私には不明)では、極大化させるインセンティブはないのかなと考えています。(続く)
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 11, 2020
税はおっしゃるとおり時間整合性あるコントロールが不可なので、「インフレ率がある閾値を超えたときに増税する」コミットメントのために利用し、インフレ率の調整は国債発行+買いオペ(直接引き受けと違って合法であるが効果は同じ)でやるように使い分ければいいのではというのが個人的な考えです。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 11, 2020
〉政治家は定量的に議論できる人ばかりである
— 音喜多 駿(参議院議員 / 東京都選出) (@otokita) January 11, 2020
み、耳が痛い…!政治家の得票インセンティブを考えると、財政出動ばかりに傾いていきそうなところがやはり私の懸念ですね。しかし、興味深い提案をありがとうございます。ぜひpolipoliで議論したいですね!私も検討してみます。
音喜多議員とはここでまとまりました。良いタイプの議論です。
ここで池戸氏も入ります。
直感的には同意しますが、そのような規範的主張をするためには定式化が必要だというのが個人的な意見でございます。https://t.co/oogansda7f
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 11, 2020
そして池戸氏と別スレがはじまります。
減税よりも公共投資の方が効果が高いです。これは乗数効果1/(1-c)とc/(1-c)の違いからも明らかです。減税ですと、消費税減税が最も効果が大きいでしょうね。 https://t.co/apnYfrYAxW
— 池戸万作 (@mansaku_ikedo) January 11, 2020
私が言ってるのはGDP増加策ではなくデフレ対策です。つまりインフレ率を上げる施策として減税のほうが効果が高い。これは租税貨幣論「貨幣価値は納税義務からくる」ので、「納税義務が低減されると貨幣価値は下がる」と言っているのと同じです。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 11, 2020
インフレ率を上げる政策としても、財政出動の方が効果的です。減税だと一部は貯蓄に回るので、その分はインフレ率を上昇させないことになります。無論、私は消費税廃止など、国民貯蓄を増やす上では、減税も必要だと考えている立場ですが。
— 池戸万作 (@mansaku_ikedo) January 12, 2020
「減税すると納税義務が低減されて貨幣価値(物価の逆数)が低下するためインフレが起こる」という話と、減税は一部貯蓄されるという話には、関係がありません。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
財政出動には「納税義務の低減による貨幣価値の低下」効果がなく、需要超過インフレは起こりますが、供給が追付けば物価は元通りです。
ちなみに池戸先生はMMTを支持しながら無税国家も可能とおっしゃっていたことがありますが、「減税すると貨幣価値が低下する」→「無税にすると貨幣価値がなくなる」ので、無税にするとハイパーインフレになります。MMTと租税貨幣論は不可分。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
ちなみにここで池戸先生のいう「財政出動」が、GDPに関してのもの(実質変数への政策)ではなく、「国債発行+買いオペ(財政ファイナンスと同等効果)」という名目変数への政策を意味しているのであれば、それはたしかに供給能力に関係なく元に戻らない物価上昇が発生します。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
池戸氏の主張はMMTではなくMMTを一部拝借した独自理論ですね。
はい、その点に関しては、私がMMTに対して、疑問を呈している部分です。無税国家も成り立つと考えています。ハイパーインフレとは、あくまでも「物不足」で起きるものなので。 https://t.co/EITaPAirmx
— 池戸万作 (@mansaku_ikedo) January 12, 2020
もう一度言いますと、物不足(需要超過供給不足)による物価変動は、物不足が解消されると元に戻ります。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
「最終的に」物価水準を変動させるのは貨幣価値の変動であって物不足ではありません。
物不足が解消されると元に戻るというのは、インフレ率(水準の変化率)が元に戻るのではなく、物価水準(水準)が元に戻ります。@otokita 池戸先生の主張はMMTではなくMMTを一部拝借した独自理論ということになります。租税貨幣論とMMTは不可分ですので。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
貨幣価値とは物で決まると考えているので、その内容には私は疑問です。貨幣価値が落ちるとは、自国通貨が大幅に安くなると定義して宜しいでしょうか? https://t.co/jDknBoDbfC
— 池戸万作 (@mansaku_ikedo) January 12, 2020
理解されているようには見えないですね。まとめますと
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
・貨幣価値=貨幣需要/貨幣供給=1/物価水準
・貨幣需要は増税で増える
・貨幣供給は国債発行+買いオペ(財政ファイナンスと同等効果)で増える
です。維新の会のように小さな政府を維持したいままデフレ脱却するには減税が解になります。
外国為替レートはあくまで貨幣価値の「比」ですので自国通貨安などは目安にするのは少しむずかしいです。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
こちらご覧ください。https://t.co/q2CVqUoqCF
貨幣価値が物価の逆数、というのはMMTは共有してないんじゃないんですかね?それだと主流派のフィッシャー交換方程式になっちゃうような。
— 道端 (@michibata7010) January 12, 2020
MMTはMMTで、労使の対抗関係やマークアップで決まるというポストケインズの物価理論を継承してるんじゃないかな。
— 道端 (@michibata7010) January 12, 2020
労使関係やマークアップ理論はイデオロギー色若干あるのであまり好きではないですが否定はしません。ただ、貨幣数量説的な考え方と矛盾もしません。
論理的にそれらは矛盾しないかと。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
物価水準は財の価値(財の需給比)と貨幣価値(貨幣の需給比)の比であり、そして財の需給比が労使の対抗関係やマークアップにより動くと考えられるので。
貨幣数量説的な考え方=リフレ派のような短絡思考にみえますが、私がリフレ派でないことは冒頭にリンクある記事を読めばわかるはずです(リフレ派とはマネタリーベース増加施策により物価目標を達成しようとする主張だとここでは定義しておきます)。
リフレ派じゃないです。以前お読みいただいた記事の冒頭にスタンス書いてあるので再読をお願いいたします。
— 木村優/Yu Kimura (@KimuraYu45z) January 12, 2020
まとめますと、池戸氏の主張はMMTというよりはMMTを一部拝借した独自理論ですね。